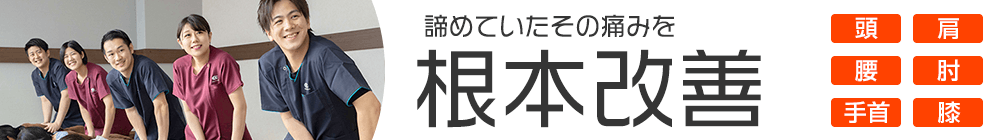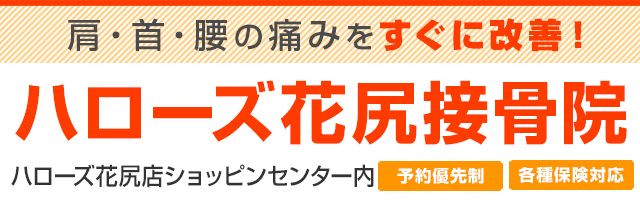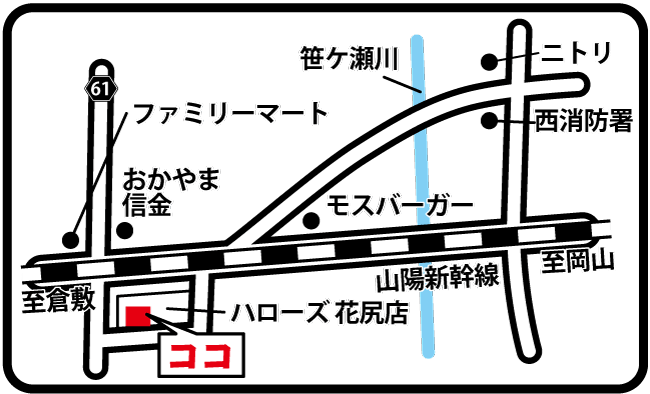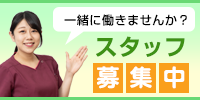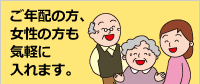肉離れ
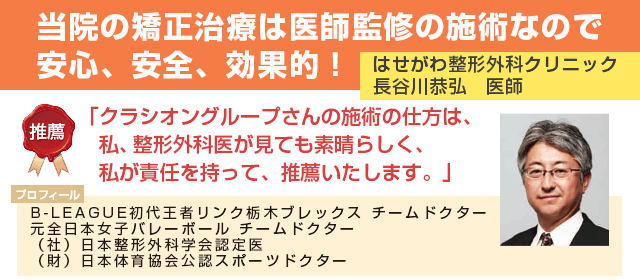

こんなお悩みはありませんか?

運動中、急に大腿の前方に痛みが出た
運動中、急に大腿の後方に鋭い痛みが出た
マラソンやスポーツなどで走ってると、急にふくらはぎに痛みが出た
運動やスポーツなどで筋疲労がある
柔軟性がなく体が硬い
姿勢が悪く、歪みが気になる
肉離れの経験があり、そこからクセがあって繰り返し肉離れが起きてしまう
運動やスポーツ競技などのパフォーマンスを高めたい
怪我をしない体をつくりたい
痛みや制限なく楽しくスポーツや運動がしたい
肉離れで知っておくべきこと

肉離れは、大腿直筋(大腿の前方)、ハムストリングス(大腿の後方)、下腿三頭筋(ふくらはぎ)に発生することが多いです。症状は、痛みがあるものの歩行が可能な軽度のものから、極度の可動域制限や陥凹などが見られる重度のものまであり、1度から3度に分類されます。スポーツ競技中に筋肉が伸ばされる(遠心性収縮)ことで発生することが多いですが、下腿三頭筋の肉離れは、30歳以降、年齢が高くなるにつれて発生頻度が増える傾向にあります。
また、皮下出血斑(内出血)は受傷後24時間以内には現れにくいことがあり、時間の経過とともに腫脹(腫れ)が出てくるのが一般的です。そのため、受傷後24時間以内に病院や接骨院などで検査を受けることが大切です。
症状の現れ方は?

大腿四頭筋の肉離れでは、スポーツや運動中に大腿前方を伸ばすような動きをした際、急激な痛みが大腿前方に感じられます。初期症状として腫脹や膝関節の屈曲制限が現れることが多いです。
ハムストリングスの肉離れは、ハムストリングスが伸ばされたときに発生しやすく、鋭い痛みや力が抜けるような感覚を伴う大腿後方の痛みを引き起こします。時には音が聞こえるような衝撃を感じることもあります。また、損傷部位に圧痛があり、股関節の屈曲制限が見られることがあります。
下腿三頭筋の肉離れは、テニスなどの踏み込み動作中に腓腹筋が伸ばされた際に発生しやすく、下腿の中央内側に圧痛や腫脹が現れることがあります。
いずれの肉離れも、腫脹は受傷後時間が経過するにつれて大きくなり、皮下出血斑は24時間以降に現れることが一般的です。
その他の原因は?

肉離れの原因としては、筋疲労や柔軟性の低下、体調やコンディションの乱れ、もともと筋損傷があったり、不適切なウォーミングアップが挙げられます。特に、スポーツや運動中に発生することが多いため、スポーツや運動の前後に行うストレッチや入念なウォーミングアップが大切です。
また、それ以外の要因として、下肢長の不一致、大量の汗をかくことで体内のミネラルや水分が不足すること、大腿四頭筋とハムストリングスの筋力のアンバランス、加齢なども肉離れの原因として考えられます。日頃から水分を適切に補給し、柔軟性を高め、疲れをしっかりと取ることも予防には重要です。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放置すると、歩行時につっぱり感が残り、歩きにくさが出る場合があります。また、血腫が形成されて硬いシコリのようなものが残る可能性や、触診や見た目で分かる陥凹が残る可能性も考えられます。さらに、軽い動作で再び肉離れが誘発されたり、繰り返し肉離れが起こることで「クセ」がつく場合もあります。
その他にも、痛みが残り、それをかばうために正常な歩行ができなくなる場合や、重症度の高い肉離れでは極度の可動域制限が生じ、膝関節や股関節の曲げ伸ばしがしにくくなることがあります。このような状態が続くと、身体の歪みに繋がることもあります。
当院の施術方法について

肉離れに対しての当院の施術は、まず急性期の肉離れには、患部を冷やすことと、EMS電気を使ってアプローチする方法があります。冷やすことは腫れを抑える目的があります。また、EMSは筋肉に刺激を与え、痛みの閾値を上げることで、痛みを軽減する効果が期待できます。
急性期を過ぎた後は、温熱療法に切り替え、患部を温める施術を行います。さらに、痛みが治まったら指圧を行い、血流を促進し、回復を早める効果が期待できる施術もあります。
また、当院では筋膜ストレッチや骨格矯正といった施術も行っており、筋膜ストレッチでは柔軟性を高める効果が期待でき、骨格矯正では姿勢や下肢長の不一致を改善することができ、肉離れが起こりにくい身体作りが期待できる施術を行っています。
改善していく上でのポイント

まず、受傷して3~5日以内では、温めることや指圧(マッサージ)をしないことが大切です。血流を促進することで腫れが悪化したり、筋肉が再断裂する可能性があるためです。最初のうちは冷やして腫れを抑えることが重要です。また、運動はせずに安静にすることが大切です。
痛みがなくなり、可動域が正常に戻ったら、軽い運動から始めることが大切です。いきなり負荷の高い運動をすると、再受傷のリスクがあります。また、運動前には入念なウォーミングアップが必要です。
さらに、肉離れを繰り返さないためにも、日頃からストレッチを心がけ、柔軟性を高めることが大切です。
監修

ハローズ花尻接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:岡山県岡山市
趣味・特技:映画鑑賞、洗車、ルービックキューブ